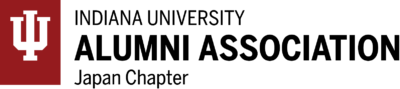第一章 ご縁が噛み合って、アメリカへ

① “斎藤先生は、「アメリカがやってきたことを実地で学べば、お前が日本に帰ってきた時に、それを生かせるのじゃないのか」と・・・”
₋ 堤先生、まず初めにIUを留学先に選ばれた理由をお聞かせいただけますか?
私はチェロを斎藤秀雄先生にずっと師事させていただいて、高校を終わる時点で先生にはもう10年間お世話になっておりました。その頃、私たち、音楽をやっている友達は、だいたい高校を出たら外国へ留学するという一つの流れみたいなものがありました。当時はヨーロッパが多く、特にその頃はフランスのチェロ界というのは凄かったですから、まあ自分もフランスに行くのかな、ぐらいに思っていたんですね。
ところが、大変な教育者であり、先見の明がおありの斎藤先生が「アメリカがいいだろう」と。「アメリカにはもちろん素晴らしい学校があり、素晴らしい先生がおられ、素晴らしいオーケストラがある。だけれども、何故自分がそういうことを、お前に言うかと言うと、いわゆるクラシック音楽の分野では、アメリカ自体がヨーロッパに比べれば後追いだ」と、もちろん日本よりは長い歴史ですけども、「アメリカがやってきたことを実地で学べば、お前が日本に帰ってきた時に、それを生かせるのじゃないのか」と。先生ご自身は、戦前ドイツに留学されましたし、「もちろんヨーロッパはいいのだけど、アメリカに行くということは音楽だけでなくて、アメリカのいろんな面ですごい所を日本に生かせるのではないのか、どうだろう?」ということでした。
フルブライト奨学資金はご存じと思いますが、当時は毎年200人くらいがアメリカに行けるようなプログラムで、それ自体も結構大きく(今のフルブライトの奨学資金の対象者は大学院生、研究家、先生とか、そういう方だけになったんですけれども)逆に言えば本当にそういう支援がないと外国に行って勉強するということも出来なかった時代でした。そのフルブライトプログラムの中にジュニア・ミュージシャンズ・カテゴリーというのがありまして、当時、戦後ずっと日本にいらしてJapan Timesに音楽評を書いていらしたマルセル・グリリー(Marcel Grilli)さんという方と斎藤先生が親しくされていたご縁からグリリーさんから、「こういうプログラムがあるのだけれども、お前の生徒の中でそういうのを受けてみる気はないか?」ということで、私にお話が来ました。
当時日本で知られているアメリカの音楽学校というと、だいたい3校しかなかった。ジュリアード、カーティスそれから イーストマン。フルブライト奨学金を頂くためには試験がありまして、私がその応募書類に書いたのもやっぱりそれしか知らなかったので、その三校を書いたのです。またその三つの学校の中で特にこの先生と言う気もありませんでした。
その後、あなた通りましたよと言われたのは、秋でしたが(1960年)、当時グリリーさんは私が演奏した時よく Japan Times に評を書いてくださっていて、そういうこともあって堤だったらいいだろうということになったと思うんです。
たまたまその年(1960年)の12月にシュタルケル先生(János Starker)が初めて日本に演奏旅行に来られたのです。 (その時ピアニストとしていらしたのがジョルジュ・シェボック先生(György Sebők)でした。)シュタルケル先生は日本で何回か演奏をされて、斎藤先生に連れて行っていただいて演奏を聴いて圧倒されたのもその通りなのですが、 実は斎藤先生ご自身が、もうこの人しかいないだろうと思われていました。シュタルケル先生はご夫妻で高輪プリンスホテルに泊まられていらしたのですけれども、斎藤先生ご自身がそこに行かれて話をされ、「自分が今までやってきた教え方のプリンシプルが非常に似ている。やっぱり堤を留学させて師事させるにはこの人しかいない」とお考えでした。私がその後高輪プリンスのシュタルケル先生のもとに伺って、奥様もいらっしゃる前で演奏を聴いていただき、 その結果、「じゃあ来てもいいよ、ディーン・ベインにも言っておくから」 ということでブルーミントンに行くことになったのです。(注:Dean Bain, ベイン(音楽)学部長)
- そうだったのですね。斎藤先生のお計らいでシュタルケル先生にお会いになったことで、糸がより合わさるというか、しっかりと決まったのですね。
② “ブルーミントンみたいなところに行って、本当に勉学に打ち込むのがいいんじゃないか”
そうですね。ただその中でも、それこそジュリアードはニューヨークだしカーティスはフィラデルフィアだし、アメリカの大都会でもあるのだけれども、逆に本当に真剣になって勉強するって、ちょっと変な言い方ですけれども、ブルーミントンみたいなところに行って、本当に勉学に打ち込むのがいいんじゃないか、という教育環境という一つの大きな理由もあったと思います。
ところで、このフルブライト・ジュニア・ミュージシャンズ・カテゴリーというのは、本当に二人枠だけの小さなプログラムで、年に全額支給が一人、それから旅費だけが一人だったのですが、幸いに私は全額支給というのに受かりまして。全額頂けると、もちろん旅費は出していただけるし、それから毎月二百何十ドルって頂けたのですね。ただ当時の二百何十ドルっていうのは、もちろん日本円に直してもすごいですけど、特にブルーミントンみたいな小さな町に行って二百何十ドルというのは、これは結構裕福なことでした。(大笑い)(注:当時$1.00=¥360)
また後で知ったのですがシュタルケル先生にとってこの演奏旅行は新婚旅行でもあった旅で、そういうのもご縁なのかなと思います。私が留学してからもなんとなく私を子どもの様にと言っては変ですが、奥様にもずいぶん良くしていただきました。
③ “本当に具体的に思ったのは、シュタルケル先生が初めてでした。“
- 話が戻るのですが、シュタルケル先生に初めてお会いになる前に、シュタルケル先生の演奏というのはお聞きになられたことはありましたか?
いいえ初めてでした。それまではチェリストといえば、フルニエ(Pierre Fournier) とか、カサド(Gaspar Cassadó i Moreu)とかね、もちろんカザルス(Pablo Casals)もいらしたけど、ヨーロッパから来られていた方が多かった、アメリカからはそんなにいらっしゃらなかったし、シュタルケル先生については無論、コダーイ(Kodály Zoltán 注:この場合はその作曲した無伴奏チェロ・ソナタを指す)のレコーディングをされたということは知っていたのですが、 特にということはなかったのです。
その日本公演では、素晴らしい完璧な演奏をされて、もう当時から完璧だったから(笑)、それはすごいなと思いました。
シュタルケル先生は、ご存知のようにハンガリー出身なんですね。若い頃から抜きん出て素晴らしいチェリストだった。ブタペストで国立歌劇場の首席チェロをされたりとか色々されていて、そういうことで駐ハンガリー日本大使と仲良かったらしいのですね、しかもそのお嬢さんにチェロを教えたこともあって、日本という国に親しみを持ってくださっていたようでした。加えて私が、出来たら師事したいということもあって、 じゃあちょっと日本人というのも面白そうだから取ってみようかと思われたのじゃないかなと思いますけども、はい。(笑)
₋ 堤先生にとってチェロの理想の先生というのはいらっしゃいましたか?
まあ、そうですね、何と言うのかな、例えばジュリアードに行ったら レナード・ローズ(Leonard Rose)という当時のアメリカでは最高の先生と言われていた方ですが、一般的ですけども、ローズ先生みたいな方に習うのかなとは思っていましたけども。
でも本当に具体的に思ったのは、シュタルケル先生が初めてでした。シュタルケル先生ご自身、その数年前に、ブルーミントンにいらしたばかりでしたから。 (注:1958年9月からIUに赴任)彼はニューヨークやシカゴでずっと活躍されていましたし。
④ “こう、いろいろなご縁が噛み合ってきたのかなあ、って思います。”
実はご縁が色々ありまして、それこそ安藤馨さん(注:IU日本同窓会創設者・初代会長)のお兄様(注:安藤膺(オサム)さん)が当時 NHK のお偉い方で、斎藤秀雄先生が、一時、新響と言っていた時代の NHK交響楽団の首席だった時に音楽担当プロデューサーでいらっしゃって、斎藤先生は、安藤 (膺(オサム)) さんとはN響を辞められてからも永く親しくされていらっしゃいました。
ご存知のように安藤さんのお母様は安藤幸さんとおっしゃって日本のクラシック音楽草分け時代の大変なヴァイオリニストでいらっしゃる。そういうご縁が重なりまして、そしたら安藤馨さんが当時のインディアナ大学のプレジデント・ウェルズ(President Wells 注:Herman B Wells、IU第11代 総長)をよく知っているから紹介状を書いてあげる、ということで実は私はその紹介状を持って行き、すぐにウェルズ先生にお会いする大変な名誉にあずかったのです。
インディアナ大学の音楽学部にとってみれば私が実は日本人の留学生としては二人目なんですが、初めての方が澤さんとおっしゃって神戸女学院を出られて修士課程で音楽学部にいらしたのです。またそれも偶然で、澤さんのお母様と斎藤先生がお知り合いで、斎藤先生が澤さんのお母様に「堤というのが今度ブルーミントンに行くからよろしく」、という事を頼まれたらしくて、その澤さんにはもう大変お世話になりました。
なんかこう、いろいろなご縁が噛み合ってきたということがあったと思います。